猫を眺めていると、スッと真っ直ぐに伸びたしっぽの子もいれば、短い尻しっぽや、くるんと曲がったカギしっぽの子も。
実はカギしっぽの猫は日本全国にいますが、長崎県では8割近くがカギしっぽだと言われています。そこには遺伝と歴史、そして江戸時代のちょっと不思議な文化が深く関わっているそう。
この記事では、カギしっぽの成り立ちや長崎との関係、さらには江戸時代の迷信まで、猫好き必見の“しっぽの裏話”をお届けします。
カギしっぽはなぜ生まれる?——遺伝子がつくる個性

カギしっぽは、遺伝子の突然変異によって生まれる“骨格の個性”です。
猫のしっぽは本来、まっすぐで長い形が基本。しかし、しっぽの骨の数が少なかったり、骨が癒合して関節の可動域が狭くなったりすると、尻尾が短くなったり曲がったりするのだとか。
カギしっぽの猫の多くは、HES7と呼ばれる遺伝子が関与していることが研究で示されています。
- 尾椎が減少 → 短いしっぽ(ボブテイル)になる
- 一部の尾椎が半分の形や癒合 → 曲がった「カギしっぽ」になる
例えば、ジャパニーズボブテイルという日本原産の短尾猫種も、同じ遺伝的要因で生まれます。
カギしっぽは病気や怪我の結果ではなく、遺伝子による自然なバリエーション。健康上の問題はほとんどなく、猫の魅力を引き立てる個性と言えるでしょう。
長崎にカギしっぽが多い理由

長崎にカギしっぽ猫が多いのは、江戸時代の国際貿易が大きく関係しています。
江戸時代、鎖国中の日本で、長崎の出島だけは唯一海外との貿易が許されていました。オランダや中国をはじめ、東南アジアとの交易も盛んで、多くの船が長崎に寄港した場所です。
当時、船には「積荷を荒らすネズミを駆除する」ために猫が乗せられており、その中にいたカギしっぽの猫たちが船員とともに出島にやってきて棲み着いたのが始まり。
やがて彼らは長崎の地で繁殖し、突然変異であるにも関わらず優性遺伝であるカギしっぽが次世代へと受け継がれていきました。
全国平均で尾曲がり猫の割合は約40%ですが、長崎では約79〜80%という高い割合を占めています。
この数字は、江戸時代から続く猫たちの“生きた歴史”の証。カギしっぽ猫は偶然ではなく、江戸時代の貿易と生活の中で必然的に長崎に根付いた存在なのです。
カギしっぽは「幸運を引っかけてくる」縁起物

江戸時代、日本では「長い尻尾の猫は化け猫になる」という迷信があり、逆に短い尻尾やカギしっぽは、「幸運を引っかけてくる」縁起物として好まれていました。
化け猫(猫又)は、長い尻尾を持つ年老いた猫が妖怪に変化した姿とされ、怪談や浮世絵にもしばしば描かれています。
この迷信から、人々は長い尻尾を持つ猫を避け、短い尻尾の猫を「安心できる存在」と見なしたのです。
江戸の町では、尻尾を短く切ったり、短い尻尾の猫を選んで飼う風習がありました。長崎で優性遺伝としてカギしっぽが広まった背景には、この文化的な好みも影響していると考えられます。
文化的背景と遺伝的要因が重なり、日本ではカギしっぽが珍しくない光景となりました。
カギしっぽの猫と触れ合う際の注意点
長崎ではカギしっぽ猫を守る「尾曲がり猫神社」が観光名所となっており、ここでは「しっぽの曲がりは幸せを引っかける形」として大切にされています。
しかし、カギしっぽは「幸運を引っかけてくる」縁起物とされる一方、扱いには注意が必要です。
尻尾の曲がった部分は骨格が特殊なため、触られると痛みを感じる猫もいます。無理に引っ張ったり揉んだりするとストレスや怪我の原因に。
カギしっぽはただの形の違いではなく、文化・歴史・縁起が詰まったシンボル。大切に見守ることが、猫との良好な関係を築く第一歩です。
まとめ
カギしっぽは、猫の個性を象徴する魅力的な特徴であり、長崎では歴史と文化に支えられて特に多く見られます。
この形は遺伝子の突然変異によって生まれるもので、健康上の問題はほとんどありません。
さらに江戸時代、出島を経由して東南アジアからやってきた猫が長崎に定着し、優性遺伝によって世代を超えて受け継がれました。
また、日本では「長い尻尾は化け猫になる」という迷信や、「カギしっぽは幸運を引っかける」という縁起の良さから、短い尻尾やカギしっぽが好まれる文化的背景も。
尻尾の曲がった部分は骨格が特殊なため、触ると痛みを感じる猫もいます。触れる際は背中から優しく撫でることが大切です。
カギしっぽは、単なる見た目の違いではなく、遺伝・歴史・文化が織りなす“生きた証”。カギしっぽの猫に出会えたら、それは小さな幸運との出会いと言えるでしょう。
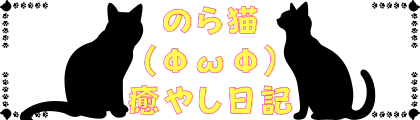


















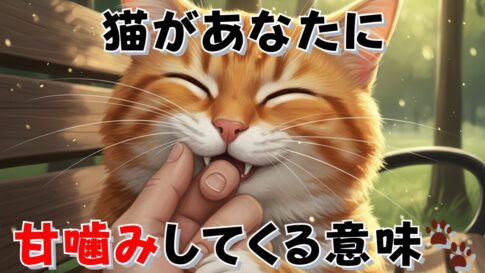




コメントを残す