猫は、いつの時代も人間に寄り添い、ときに神として崇められ、ときに魔性の存在として恐れられてきました。
その歴史は非常に古く、人類が農耕を始めた頃にまでさかのぼります。今回は、猫がどのように人と関わり、世界各地に広がっていったのかを振り返ってみましょう。
猫の家畜化はどこから始まった?
猫と人間の関係は、約1万年前の農耕の始まりとともに誕生したと言われています。
人類が穀物を蓄えるようになると、それを狙ってネズミが集まり、そのネズミを追ってやってきたのがリビアヤマネコでした。
人にとっても猫にとっても利益のある関係が築かれ、やがて人の暮らしに自然と溶け込んでいったのです。これが、現代の「イエネコ」の始まりと考えられています。
約9,500年前のキプロス島では、人と一緒に猫が埋葬された痕跡が見つかっています。これは、猫が単なる害獣駆除役を超えて、人間の生活に深く関わっていたことを示す最古の証拠です。
猫の家畜化は、猫自身が人間社会に順応し共生を選んだ「半家畜化」と呼ばれる特別な形でした。
古代エジプト|神の化身として崇拝された猫

古代エジプトでは、猫は単なる家畜ではなく神聖な存在として崇められていました。壁画や遺物には猫の姿が多く描かれ、家庭で人と共に暮らす様子も残されています。
猫はネズミを駆除する頼もしい存在であると同時に、女神バステトの化身として信仰の対象にもなりました。人々は猫を守り、敬意を払うようになっていきます。
また、飼い猫が亡くなると家族全員が喪に服し、葬儀を行ったと伝えられています。亡骸はミイラとして保存され、猫専用の共同墓地に埋葬されるほどでした。
こうして古代エジプトにおいて猫は、人の暮らしと精神世界の両方に欠かせない存在として位置づけられていたのです。
ギリシャ・ローマ|交易で広がる猫の存在

エジプトでは猫の国外持ち出しが禁止されていましたが、商人たちの手によって猫は密かに運ばれ、古代ギリシャやローマへと渡っていきました。
古代ギリシャではおよそ2500年前、古代ローマでは約2000年前には猫の存在が確認されています。
ただし当時のヨーロッパでは、ネズミ捕りといえば主にフェレットが活躍しており、猫はそれほど重視されていなかったようです。
エジプトほど神格化されることはなかったものの、猫の存在は静かに地中海世界へと根を下ろしていったのです。
中世ヨーロッパ|キリスト教と猫の迫害

やがて猫はヨーロッパ全土に広がり、中世にはネズミ退治の能力から人々に重宝される存在となっていきました。しかし、キリスト教の拡大とともにその立場は一変します。
もともと土着信仰の中で神聖視されていた猫は、異教の象徴として忌み嫌われるようになりました。特に夜行性で人に従順ではない性質から、悪魔や魔女の化身とされることも。
魔女狩りの時代には、猫までもが迫害の対象となり、虐待や火あぶりに処されるなど、多くの悲劇を経験しました。
それでも猫は人間の生活から完全に消えることはなく、人知れずネズミ退治のパートナーとして生き延び、現代へとつながっていきます。
イスラム世界|預言者と猫の共生
中世ヨーロッパで猫が迫害されていたのとは対照的に、イスラム世界では猫は非常に大切にされていました。
イスラム教の開祖であるムハンマドが猫好きだったという逸話は有名で、預言者の膝の上で眠る猫を起こさないよう、衣の袖を切ったという話まで伝わっています。
そのためイスラム圏では猫は「清浄な動物」とされ、家やモスクに自由に出入りすることが許されました。
今でもトルコやエジプトの町を歩けば、モスクの中でのんびりくつろぐ猫たちの姿を見ることができます。
インドにおける猫|宗教観に揺れた存在

猫の評価は、宗教的な背景によって大きく変わってきました。
仏教では、ブッダが入滅した際に猫と蛇だけが泣かなかったとされ、仏典には猫が「保護すべき動物」として明記されず、他の動物に比べ評価が低かったといわれています。
さらに、ヒンドゥー教では「唾液は不浄」とされるため、頻繁に毛づくろいをする猫は嫌われがちでした。
ただし実際には、僧院では猫が飼われ、経典や食料をネズミから守る役割を担っていました。宗教的に特別視はされなかったものの、現実の暮らしには欠かせない存在だったと言えます。
中国|魔除けとして信じられた猫

猫が中国に伝わったのは約2000年前といわれています。唐や宋の時代には、写実的な猫の絵が多く描かれ、すでに人々の生活に深く関わっていたことがわかります。
当時の中国では、猫は「悪霊を払う力を持つ」と信じられていました。そのため、全国各地で猫を模した魔除けが作られ、家庭や寺院に置かれていたと伝えられています。
特に夜行性で目が光る猫の姿は、邪気を退けるシンボルとして人々に心強く受け入れられました。
また、文献には猫が米倉を守る存在として記録されており、農耕社会においても重要なパートナーだったことがわかります。
日本|福を呼ぶ縁起物へ
猫が日本にやってきたのは奈良時代から平安時代にかけてだと考えられています。遣唐使が仏教経典を持ち帰る際、その経典をネズミから守るために猫を同行させたのが始まりとされます。
やがて「福を呼ぶ存在」として縁起物の地位を築いていきました。特に江戸時代には「招き猫」が誕生し、商売繁盛や家内安全を願うシンボルとして庶民の間にも広まりました。
さらに、日本の猫信仰は地域性も豊かです。「猫神様」を祀る神社が各地に存在し、漁村では豊漁祈願、農村では豊作祈願の対象となるなど、人々の暮らしに密接に結びついていました。
日本における猫は、害獣を退治する実用的な存在を超え、人々に「福」と「癒し」を与える特別な存在へと進化したのです。
まとめ|人と共に歩んだ猫の世界史
猫の歴史を振り返ると、その姿は時代や地域ごとにさまざまな意味を持ってきたことがわかります。
猫は常に「ただの動物」にとどまらず、人間社会の価値観や宗教観を映し出す鏡のような存在だったといえるでしょう。
そして現代、私たちが街角や家の中で猫と触れ合えるのは、1万年にもわたる長い共生の歴史があったからこそです。
気まぐれで自由奔放、それでいて人を癒し魅了する――そんな猫の姿は、これからも変わることなく、世界中で愛され続けていくはずです。
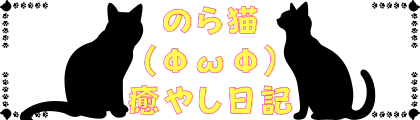

















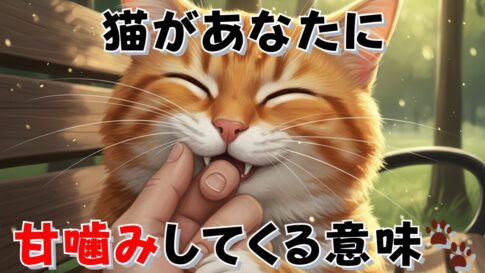




コメントを残す